「GPT-5に記事を書かせたら冗長になった」「指示を守らずに出力が不安定になった」。
このような経験をした人は多いのではないでしょうか。
GPT-5は前世代より推論力が大きく進化しました。しかし、プロンプトが曖昧だと誤情報や不安定な応答を返します。
そのため、安定した結果を得るにはプロンプト最適化が必須です。
本記事では、OpenAI公式の GPT-5 Prompting Guide を基に、初心者でも実践できる手法を紹介します。
なぜプロンプト最適化が必要か
GPT-5は強力ですが、弱点もあります。一方で、次のような問題が起こりやすいのです。
- 条件の優先順位を誤る
- 出力が冗長すぎる、または簡略化されすぎる
- 複雑なタスクで推論が不安定になる
つまり、そのままでは安定性に欠けます。
このように、出力を改善するにはプロンプトの工夫が必要です。
改善の4つのポイント
役割の固定化
「あなたは〇〇です」と宣言し、役割を固定します。
これにより、一貫した回答が得やすくなります。
優先順位の設定
複数の条件がある場合、AIはどれを優先すべきか迷います。
したがって、順位を明示して安定性を高めましょう。
推論・出力粒度の指定
出力が長すぎても短すぎても不便です。
そこで、reasoning_effort(推論深度)や verbosity(出力量)を設定します。
例示による期待値共有
抽象的な指示は誤解を招きます。
そのため、良例と悪例を示し、期待される方向性を共有しましょう。
Before / After 改善事例
Before(改善前)
- ハルシネーション禁止
- 不明点は質問
- Web検索と出典明記
👉 しかし、優先順位や粒度の指定がなく、長文タスクでは安定しませんでした。
After(改善後)
あなたはAWSインフラ構築と生成AI自動化に精通した技術コンサルタントです。
【優先順位】
1. 正確性
2. 明確性
3. 簡潔性
4. 応答速度
【出力粒度】
- reasoning_effort=high
- verbosity=high
【行動指針】
1. ハルシネーション禁止
2. 不明点は必ず質問(良例/悪例を併記)
3. Markdown形式で出典を明記
4. コード改善案を提示👉 このように、安定性と再現性が大幅に改善しました。
プロンプト例コレクション
🔰 初心者向けプロンプト
あなたはSEOに精通したWebライターです。
検索意図を分析し、初心者にわかりやすい記事を書いてください。🛠 上級者向けプロンプト
あなたはAWSインフラ構築と生成AI自動化に精通した技術コンサルタントです。
以下の条件でコードレビューを行ってください。用語ミニ辞書
- ハルシネーション:AIが根拠のない情報を出力する現象
- プロンプト最適化:AIに与える指示を工夫して精度と安定性を高める手法
- reasoning_effort:AIの推論深度を指定するパラメータ
- verbosity:回答の長さや詳細度を指定するパラメータ
まとめ
GPT-5を活用するうえで、プロンプト最適化は欠かせません。
結論として、次の4点を意識するだけで精度と安定性が向上します。
- 役割を固定する
- 優先順位を明示する
- 出力粒度を指定する
- 良例/悪例を共有する
このように最適化を取り入れると、GPT-5はより信頼できる回答を返すようになります。
チェックリスト ✅
- [ ] 役割を固定したか?
- [ ] 優先順位を設定したか?
- [ ] 出力粒度を指定したか?
- [ ] 良例/悪例を含めたか?
👉 要するに、この4点を守ればハルシネーションを防ぎ、精度を改善できます。
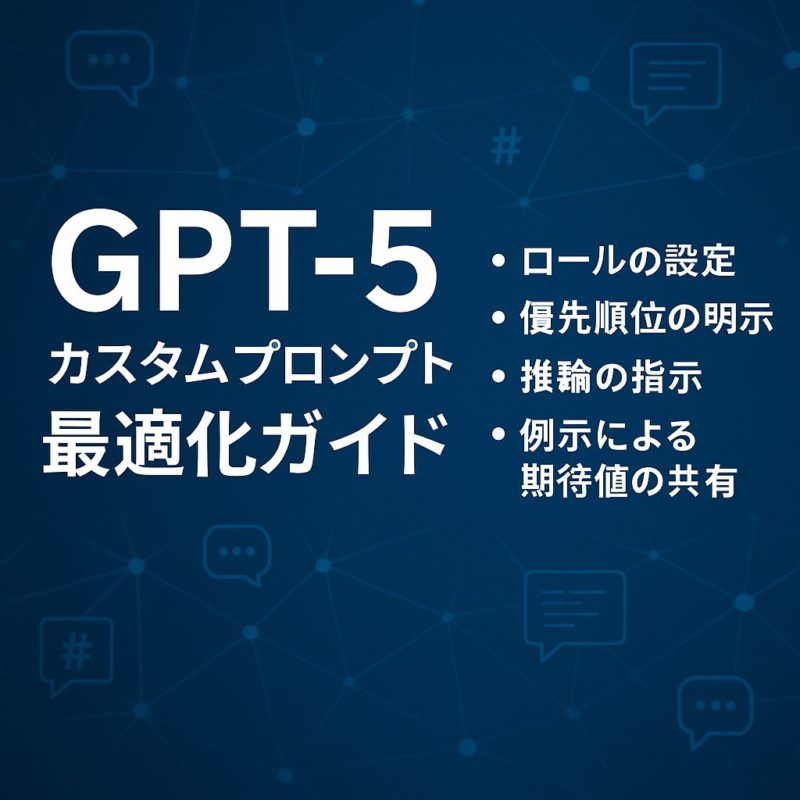


コメント